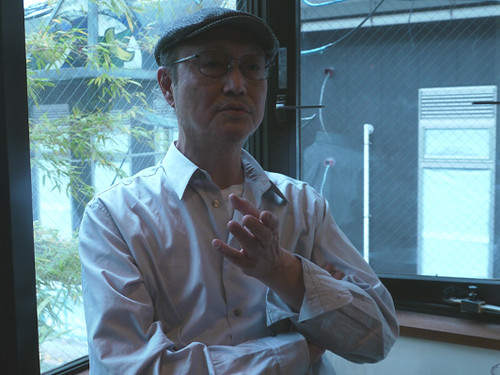映画『ライフライン』より
女性監督による製作・上映集団“桃まつり”による上映企画などで注目を集める渡辺裕子監督が、石橋蓮司と安藤サクラを迎えた新作『ライフライン』を完成。5月28日(土)より渋谷アップリンクXにて公開される。渡辺監督の過去作品も連続上映されるこの特集上映にともない、地球外生命体に侵されたゾンビが闊歩する日本で巻き起こるホームドラマという破天荒かつほのぼのとした『ライフライン』に出演したふたりの俳優に、今作について、そして独自の演技への思いについて話を聞いた。
現場では100の理論がある。それを滲み出せているかどうか、経験的に掴みとるんだ。(石橋蓮司)
── 石橋さんの活動はメジャーの作品から今回の『ライフライン』のようなインディーズの作品、さらにはゲームソフトに出演したりと、ほんとうに幅広いですが、60、70年代と比べて、この映画に出たいという基準は、変わってきているところはありますか?
そんなに大きく変わらないですね。女優と違って、男優っていうのは自分からなにかを演じたい、人物像を通して社会と対話したいとあまり思わないんだよね。それはひとつは、自分が劇団(劇団第七病棟)をやっているということがあるのかもしれないけれど。なんの粉飾もなく自分を語ろうというときは演劇をやります。言いたいことが自分のなかにあって、それを演劇という表現のなかで、こういう切り口でやりたいなというときです。映画とかテレビといった媒体は、あまり自分からなにかそこで発言できるというものじゃなくて、与えらえたもののなかから切り口を探していく。たぶんこういうかたちでやってもらいたい、というものがあったら、そうじゃないもうひとつ違う入口から入ってみて、ちょっと向こうの考えよりも広げてみようとか細工はするけれどね。だから自分からこういう役をやりたいというのはあんまりないんです。
石橋蓮司氏
ただ60年代70年代で俺は自分は異端と思ってはいないけれど、よそからは異端と言われてるんだなということがあった。そういうことで年齢を経ていくと、異端じゃなくて正系のほうもやらされることがあるけれど、異端と正系というのはそんなに違いはなくて、時代性の問題であって、そのときのひとつの世相であったりということで正系が入れ替わるだけであって、本質的には一緒だということが解ってくる。一生懸命生きようとすると、ある時代には異端であったり、ある部分では正系であると思うんだよね。だから、人間が決めていくことを少し茶化せたらいいなと思うんです。最近は茶化してばかりいて、あんまり本質を言ってないけど(笑)。
── そのほうがフットワーク軽く活動できるのですか。
そういうことだね。本質的な生き方って今あまりないと思うんだ。60年代70年代は自分の生き方で大きく世界とやりあえるようなことがあったと思うんだよね。だから自分を試すとか、自分の理想を探すとか、自分がどこに依って立つべきなのかみたいなことを、作品を通して社会に対して、世間に対して挑んでいくことによって、自分の居所を探すというところがあった。
でも80年代以降というのは、やっぱり世の中が大きく変わったことがあって、自分が何者であるかを探すのがものすごく難しいんですね。だから出てくるものに対して「えっその日に決めちゃうの」って。「これが本質なの?」「これは現象じゃないの?」って茶化していくことで俺自身が面白がっていく。これは成功すればいいけどね、成功しないとバカじゃないのって思われちゃうから。
── 70年以降に生まれた者にとっては、アートと政治がすごく密接に結びついていて、なにかを変えられるんじゃないかという思いがあった70年代にすごく憧れがあるんです。
確かに幻想だったのかもしれないし、青臭い理論だったのかもしれない。つまり政治的ラディカリズムと芸術的ラディカリズムがすごくクロスして、一緒にやれるものだという考え方があった。ものすごく政治を一生懸命やるやつと、ものすごく演劇や絵、建築を一生懸命やるやつ、みんな一緒にひとつのことについて語り合ったし、激しくぶつかりあってやることができたからね。お互いに刺激になったし、すごく勉強になった。でも今はあんまりクロスしていくことはないかなぁと思って。あまり人と喧嘩をしたりという時代でなくなったというか、「そういう考え方もあるんじゃない」で収めちゃうみたいなね。
── 違う考えの人同士が繋がっていかないと。
だから、昔は繋がらないとできないということがあって、例えばひとつ監督に作品を提供された場合に、「これはどういう意味でやるんですか」とか「なんの意図があるんですか」、そういうことを平気でやりあって、一緒に同罪になるというか、ひでえ作品に出たのも同罪だし、面白い作品に出たのも同罪だと(笑)。大作、小作、独立系を含めて、自分がその作品に参加することについて、すごく意味を求めていた。だからひとつの表現に対して思い入れを強くやったものです。そういう意味では、人と人がひっつかない。違うものだということを解り合いながらやるということだね。
── 最終的なところで人と人とは解り合えないという諦念からはじまるということですか。
いや、まず解ろうとするんだけれど、やっぱり解らないでしょ。親子や夫婦だってうまくいかないんだから、うまくいくわけないんだけれど、お互いの立場とかものの考え方、びっくりするような考え方をするとか、やっぱり俺たちが自己中心的に世界を把握しようとしてしまうんだよね。で現実は違うということを知って、またひとつ幅が広がるというかね。とにかく男と女の関係でも、人との結びつきというものをいちばん別格にとってたよね。
── そうした作品への思い入れの違いは、今の日本映画の質にも影響していると思いますか。
観客の問題もあるんだと思うんだよね。俺たちの時代って観客が熱いんだよ。ヤジ飛ばしてくるわけだよね。同調したときは拍手するし、スクリーンに向かって「ナンセンス!」とかって、それくらい熱い。今のパソコンで悪口言ったりそういうんじゃないよ、もっと本質的にぶつかっていく。俺たちも観客のその熱さはどこに根っこを置いてるんだろう、何を求めてるんだろうって考える。こっちも油断してムードに乗ってやると「バカ!」って言われちゃうんで、気をつけてた。
自分の今までの知恵で、例えば今回の渡辺監督でも、前の作品を見させてもらえば、何をしたいっていうのを俺の感覚で確認する。それが正しいかどうか当たっているかどうかは別にして、そして現場でやってみるのがいちばんいいんだ。現場っていうのは舞台だから、そこで100の理論があるかもしれない。それを滲み出せているかどうか、経験的に掴みとる。
それから、意外と相手が軽くやっていて、ものすごく本質をいってたりする場合だってあるんだよね。俺たちは意味付けをしてやりたくなっちゃうけど、軽くポッと捨てるようにやる、というのもすごく大事なことだと思うこともあるしね。
そういう意味では、若い人とやるときの面白さはありますね。いいかげんな人も多いけど。「こういうことを今やろうと考えるなんて、どんなやつだか見てみたい」って理由で引き受けて、「ほらみろ、だめじゃないか」ということだってあるんです。
映画『ライフライン』より
── 映画制作に携わる若い世代の人たちに共通する感覚があるとしたら、なんでしょうか。
世の中のこと知っているよね。昔は父親とも世代間みたいなのがすごくあったんだよね、ギャップがあった。俺はそういうのはぜったい感じないんだろうと思っていたけど、価値観が違う。特に今は情報量の所得が違うから。昔はおやじや兄さん世代が所得している情報の質みたいなものがだいたい解った。ここから取ってるとか、こういう傾向で読もうとしてるなとか、こういうのはテレビ的問題だなとか。でもコンピューターによって、明らかに置かれましたね。つまり違う社会になってしまった。自分の距離がぜんぜん解らないよね。だから、新聞を読んだりしても、リビアでああいう問題が起きたり、世界でいろんな動きが起きるけど、昔は俺は本来的にはそこに関わってたはずなんだよね。ベトナム戦争であろうと、世界的なことに日本からの発信を自分たちの身体を使ってやったんだ。世界はそんなに遠くなかったんだけれど、今はぜんぜん自分と関係ないところから物事が起こりはじめている。そういうことで置かれたなって、置かれたってことは遅れたってことじゃないんだけれど、違うところにいってるなって、今からでも(ネットを)やればいいんだけれど、むかつくからね(笑)。
──現場に運んだり、運動や活動に参加して体感したものっていうのはすたれないですよね。
身体は歴史を持っててね、身体は物質的だから、そういう自分の辿ってきた年代なりぜんぶ身体に溜め込む。頭は嘘はつけるんだけれど、身体は嘘をつかないからね。絵かきなら絵に描く、音楽家なら音楽を作る、俺たちはそれを身体化していくのを職業としている。そのときに、どうやっても体は嘘をつかないんだよね。そのことが、例えば若い人たちが特に、その身体が欲しいという場合もあるんだ。それはある意味歴史だから、撮る側の意図と身体とのギャップが面白いんだよね。
生理感覚がだいぶずれているんだろうね。例えば好きという言葉だって、表し方が違うんだよ。俺たちは好きだっていうと、ちょっと暴力的になったりする、つまり、身体的に触れようとする。今は触れないで眺めているみたいなことで、触れ合うとゴチャゴチャするとか汗臭くなるからということもあると聞いたから、「バカじゃないの」って。
今の若い人たちは頭がいいんだよね、きっと。空気読みが早くて、パーッと解釈できてしまうけれど、俺たちは鈍かったから、とにかく必死に行動するしかなかった。
映画『ライフライン』より
── その一方で、新しい世界の見方をしている若い人たちに可能性も感じていらっしゃるんですよね。
それはあると思う。それと逆に、ものすごくエゴイスティックなんだろうけど、すぐに一緒になれるのは、すごくインターナショナルだなって。自分たちの特異性とか、俺の独自性とか個性とかってみんな持ってるのに、それを流してもいいみたいな。非常に違うつながりができるのかなって。日本人だと言わないで済んじゃうとかね。みんなと一緒でいいという、感覚的にグローバル。
ただ飽きっぽい、責任持たなくなっちゃうからさ。俺なんか70年代やったことをまだひきずって逃れられないから、余計こだわったりつっぱったりする。でも今の人はこだわる必要がないんだろうね。
── 石橋さんが演じる役柄って、常にその作品におけるひっかかりというか、異化作用というものがあると思うんです。
それしか生きられないんだね。呼吸のしかたをしらない。それでも戦後から60年くらいだから、それが普通の生き方だったんだと思うんだよね。2000年になってから、自分が芝居をうてなくなった。演劇をやることはそんなに難しくないんだけれど、言いたいことがないんだよね。芝居だけはせめて俺のやりたいことはこれだということをやりたいので、そうすると言いたいことがないものだから探して「これかな」、と思ったときは俺がもう飽きちゃう(笑)。でもシェイクスピアとかチェーホフとか古典をもってきちゃうのはいやだなと。なんとか新作をやりたいなと。演出家、企画者としては芝居をやることはできるかもしれないけれど、俺は役者だから、身体でうそはつけないから。
── そこはもどかしさがありますか。
例えば孤独という問題があって、この『ライフライン』という映画だって孤独の話だけど、俺が考えているもうひとつの孤独っていうのは、思想的な問題があるから。なにを捨てていっているのか、捨てられたものとしてのものをやりたがるんだ。捨てていくことはいけないと思わないんだけれど、捨てられた側はどうするんだみたいなこととかね。それは必ずリバウンドで、廃屋の写真を撮る人とか、捨てられた人たちを撮る人とか出てくるものだけれど。たぶん魂の問題だと思う。
映画『ライフライン』より
── 渡辺監督の作品で今回の二郎という役柄については楽しんでできましたか。
さっきの話じゃないけど、こだわるというか、自分の生きてきたことにこだわる、ということがある。それは俺もよく解るし、この世代じゃないと解らないだろうし、また逆な意味でいえば、若い子のひきこもりについて、なんの経験もしていないのに、外に出てみないとそこがいちばんいいかどうか解らないじゃないかって俺は思っちゃうんだけど、彼らにはそれなりの理由がある。この物語は別にひきこもりじゃないんだけど。
弱者側が勝手にストーリーを作るとすると、例えば戦争のときどういう生き方をしてきたんだろうとか、社会とどうやって関わってきたんだろうとかあるじゃない。ラストで、なぜ自分が命を落としてまでもそういうことをやりたいと思うのか、この人のお父さんの世代やお兄さんの世代はどうだったのか。自分では一回もそういったところで、勇ましく国家とか社会を語らずにずっと眺めていた人間、無難に生きてきた人間について、それは平凡こそ真実だからいいんだけど、なにか自分のなかでやるせなさとして持ってたのかな。
二郎という役についは、女房が死んだということが大きな箍が外れることなんだろうけれど、なにかきっかけがほしかったのかな。男ってそういうものを持ってて、「俺だってよ…」っていうことがあるんだよ。それが今回ちょっときっかけでやぶれていってみた。こういうことだってあるよなって。これは俺の勝手な考えだけれど。
── 安藤さんとのコンビネーションはいかがでしたか。
ホン(脚本)を読んで、さらに安藤くんという素晴らしい女優さんと一緒だったので、余計いろんなことが考えられた。彼女は世代の違いじゃなく、解り合える。役者同士ってそういうところあるから。同じ種族だと思うんだ。そういうときは理論的じゃなく、生理的にふっと交渉しあえるんだよね。そういうことがありました。安藤くんとやれるということで二重に喜んでやりました。
── 主人公が行動を起こすまでのためらいと、瞬発力が物語の原動力となっています。
安藤くんのたきつけもいいよね。なにかの血を騒がせないと、それが起きない。彼女が持っていた表現が、役を通して煽る。自然にやれてしまうということはありました。彼女はすごいパワーがある。
── 最後に、渡辺監督の演出についてはいかがでしたか。
勝新太郎とかもそうなんだけれど、俺は短編には短編の才能があると思うんだよね。もうちょっと中編を作ってもいいと思う。やったときどんな力を発揮するのか、観てみたいね。失敗してもいいからやってみてその差異を生理的に知ってほしいな。
(インタビュー・文:駒井憲嗣)
退屈なときが楽しかったりする(安藤サクラ)
── 石橋さんとの共演で、どんな刺激を受けましたか。
安藤サクラ(以下、安藤):石橋蓮司さんとの共演は、やはりとっても緊張しました!石橋さんは、この作品がこうしたらいいんじゃないか、というのを具体的にいろいろ考えていらっしゃったので、私にも「こうしようと思うんだけれど、おまえはどう思う?いいだろう?」という会話をしてくださったり。そういう方と一緒にお芝居できる機会は、そうないので。常に「私、石橋蓮司さんと一緒にお芝居してる」と、思って感動してました。
安藤サクラ氏 撮影:荒牧耕司 ヘアメイク:星野加奈子
渡辺裕子(以下、渡辺):安藤さんが演じる中国人のホームヘルパー、ホイさんが「もうお前なんか知らない」って部屋に篭ってる間、その後の推移みたいなところで、いろいろアイディアをいただきました。はじめ、脚本でホイさんと二郎というのは対立事項としてだそうとしたのですが、すごい優しい雰囲気が部屋の中に流れているのは、ふたりのキャラクターが似てる、魂が似ているのかな、というのは思いました。
安藤:でも仲よさそうでしたね、思ったより。
渡辺:私も演出が追いつかなかったところがあるのかもしれないですけれど、でも父と娘くらいに見えたという意見があるのは、そういうところがあるのかなって。
── 観客としての今作に対する感想は?
安藤:私これ観終わってまた観たいと思いました!この物語の続きじゃなくて、これを何回も観たい。自分のことはぜんぜん印象残ってなくて、石橋さんの最後の顔。うわあかっこいい!監督すごいなって思った。
渡辺:映画っていろいろあると思うんです、きたない部分を掬う映画もあるし、人間の本性を暴きたいと、自分もそういうことをやっていると思うんですけれど、これは人間のいい部分を描きたいなと思った。そのあたりでは、精神的にはすごい楽でしたね。きれいに、かっこよく撮ればいいんだと。
安藤:観ていて後半、とっても楽しかった。それも、もっと続くんじゃなくて、これぐらいがちょうどいい、終わり方が絶妙でしたね。
映画『ライフライン』より
渡辺:役者っていつもリアクションしないといけないですよね、動かなくなったら素敵な被写体じゃなくなる。つまんないって顔をされたらほんとうにつまらなくなると思うんですけれど、安藤さんがつまんないことってなんですか?
安藤:特にないです。「この映画が退屈だなぁ」とかはあります。でも退屈なときが楽しかったりする。あぁーやりたくない、って思ったりとかあぁーなにこれ超はずかしいと思っても、(よく考えてみたら)きっと楽しいんだろうし、意外とそういうのが良かったりもするかもしれないし。とってもいやなときってありますけれど、けっこう甘ったれで、こうしてくださいって言われたら、はい、こうしますって感じだから。
渡辺:安藤さんには、こういう人いるって思わせる存在感がある。役者さんてカメラの前にいることだけが重要なことだと思うんです。ちゃんとそこにいるというか、演技じゃなくていられる人。
渡辺裕子監督 撮影:石川ひろみ
── 現場でなにも制約がない、好きなことをやっていいよ、といわれたときはどうしますか。
安藤:好きなことをやれ!と言われれば好きにしますよ。でも調子にのって好きなことを楽しむのは好きではないです。
──仮になんでも作っていいよ、という条件があったときに、それでも安藤さんは演じるということをで欲求を満たしていくんでしょうか?
安藤:あまりそういうふうに考えたことはないです。演じることによって自分がどうのこうのっていうのはあまりよく解らない。……いまちょっといろいろ考え中です。いろんな考えも変わってくるでしょうし。
──たいへんな現場でデビューして、いい作品にたくさん出て、俳優としていまどんな段階だと思いますか?
安藤:そこまでやってないです。これしかやってないから、なにも結論なんてだせないところですね。あと何十年やってみたときにもう一回聞いてみてくださいっ。まだ25歳だし。
── これからキャリアを重ねていって、こういう歳のとり方、こういうおばさんになりたいというのはあります?
安藤:しわくちゃなおばあちゃんに憧れます。フフフ。私太りそうだから、あまり太るのもよくない。というのもあるし、でもおいしい食べ物を食べたい(笑)。結婚して夫婦仲良く、旦那さんがいて子供がいて、ちょっとお庭の手入れをしてみたいな感じがいいかなと思いますけれど。
── 女優としては?
安藤:生活が充実していつつ、お仕事できたらそんな贅沢はないと思います。
映画『ライフライン』より
── 普段の暮らしが豊かであれば、それが演技にも滲み出てくる、そういうものだと感じますか。
安藤:自分が映るものですからね。だから、やっぱり体をいたわり、普段の生活が大切なのではないかと思います。
渡辺:いい映画って、ぜんぶ暮らすことが映っていると思うんですよ。非日常も多いですけれど、でも非日常を暮らすことが必要で。
── 『ライフライン』は二郎とホイさんのふたりの暮らしのディティールが印象深かったです。二郎が向かう仏壇とか、二郎が玄関で靴を履いて出ていくところとか、暮らしている人がいて生まれるたたずまいがちゃんと描かれているなと。
渡辺:もっとやれたなと、もっと暮らしって豊かだろうなと思っていたんですけれど、そういうことができたらいいなと思いました。
── 安藤さんは映画を観るときは超現実的な映画とファンタジーと、どっちが好きですか。
安藤:どちらも好きです。でもファンタジーの方が気になる!!
渡辺:安藤さんが自分の顔じゃなくて映画に出るってどうですか。表面が自分でなくなったとき、役者さんてどういう演技をするのかなというのに興味があるんです。
安藤:やりたいやりたい、ブサイクブサイクばかり言われてるので、やってみたい!!
渡辺:それはブサイクな役をできるっていうことがすごいんだと思います。
安藤:当て書きにしましたから、と言われてブサイクって書いてあったりするから、もう納得している事実です。でもどこかの時代にいけば、わりとモテたと思う(笑)。あまりにブスブス言われたから、もういやとも思わないし、それは置いておいて、自分の顔を変えられて映画にでられたらいいなとずっと思ってました。あと顔の癖とかもあるから、自分じゃない顔の筋肉で演技してみたいなって。顔の筋肉が勝手に動いちゃうので。
── それは女優としての才能ですね。
安藤:これからもいろんなことに挑戦していけたらいいな。
(インタビュー・文:駒井憲嗣)
石橋蓮司 プロフィール
1941年、東京都生まれ。劇団若草、劇団青俳、現代人劇場などを経て、現在は劇団第七病棟主宰。演劇・映画・TVドラマにおいて、強い個性と圧倒的な演技力で異彩を放つ。代表作として『火宅の人』(1986年)『浪人街』(1990年)『鉄道員』(1999年)『オーディション』(2000年)『日本の黒い夏―冤罪』(2001年)『北の零年』(05年)『人間失格』(2010年)など。北野武監督作『アウトレイジ』(2010年)、行定勲監督の『今度は愛妻家』(2010年)で第53回ブルーリボン賞助演男優賞を受賞。
安藤サクラ プロフィール
1986年、東京生まれ。2007年、父、奥田瑛二監督作品『風の外側』のヒロイン役で映画デビュー。以降立て続けに話題作に出演。2009年『愛のむきだし』で高崎映画祭最優秀新人賞、ヨコハマ映画祭助演女優賞受賞。2010年『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』でアジアン・フィルム・アワード助演女優賞ノミネート。同年5月に舞台『裏切りの街』に出演、6月に『サイタマノラッパー2』が公開された。
渡辺裕子 プロフィール
1981年生、愛媛県出身。武蔵野美術大学卒。映像制作会社でのAD修業を経て、05年に東京芸術大学大学院映像研究科に入学。黒沢清監督、北野武監督に師事。修了後、同大学院の後進の制作指導に関わりながら、映画を制作。主な監督作品に同大学院製作のオムニバス映画『新訳 今昔物語』の一篇『Wrestler Jeanne』、『エイリアンズ』、NPO映像メディア創造機構製作作品の『UBIQUITOUS』がある。2010年の桃まつりpresents 嘘に参加し『愚か者は誰だ』を上映。その『愚か者は誰が』がSSF x CoFesta PAO アワードを受賞し、2011年の今年、短編映画『ライフライン』を制作した。
『ライフライン』【渡辺裕子過去監督作同時上映】
2011年5月28日(土)~6月3日(金)連日21:00
渋谷アップリンクX
料金:当日¥1.300/前売¥1.000/学生¥1.100/シニア¥1.000/
Twitterでツイートした割引¥1.000 ※Twitterで今回の上映のことをツイートしたと自己申告した人を割り引きます。
【上映プログラム】
5月28日(土)『UBIQUITOUS』『愚か者は誰だ』『ライフライン』(計90分)+トーク
●ゲスト:深田晃司(映画『歓待』監督)×渡辺裕子
5月29日(日)『ライフライン』『愚か者は誰だ』『惑星ブーケ』(計89分)
5月30日(月)『ライフライン』『愚か者は誰だ』『UBIQUITOUS』(計90分)
5月31日(火)『ライフライン』『惑星ブーケ』(計61分)+トーク
●ゲスト:安藤サクラ(女優)×渡辺裕子
6月1日(水)『ライフライン』『愚か者は誰だ』『惑星ブーケ』(計89分)
6月2日(木)『ライフライン』『愚か者は誰だ』『UBIQUITOUS』(計90分)
6月3日(金)『ライフライン』『UBIQUITOUS』(計62分)+トーク
●ゲスト:冨永昌敬(映画監督)×渡辺裕子
『ライフライン』
キャスト:石橋蓮司、安藤サクラ
プロデューサー:金森保
脚本:渡辺裕子
キャスティングプロデューサー:城戸史朗
VFXコーディネーター:小田一生
撮影:四宮秀俊
照明:玉川直人
録音・効果・選曲:有元 賢二
編集:山本良子
制作:キリシマ1945
19分/HD/16:9/2011年
『ライフライン』公式HP