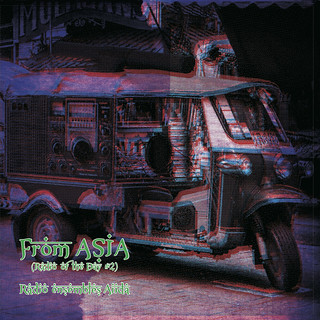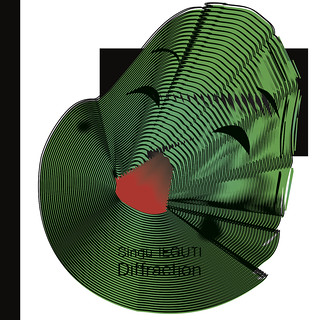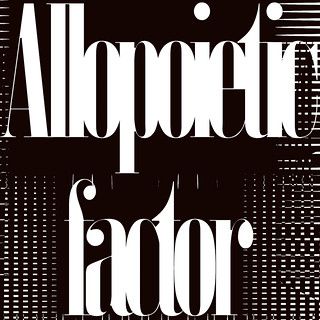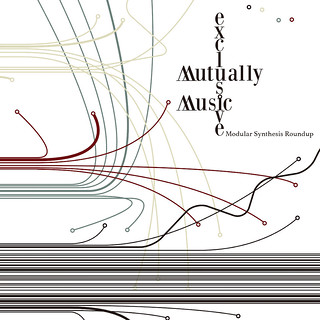EP-4の佐藤薫が設立したレーベル『φonon(フォノン)』。今年は通算8枚のCDをリリースするなど活発な活動を続けるこのレーベルについて、webDICEでは思想史家の市田良彦氏によるアニュアル・マニフェストを掲載する。
2018年初頭に発動した『φonon(フォノン)』は、EP-4の佐藤薫が’80年代に立ち上げたカセットテープ・メディアを中心としたインディー・レーベル『Skating Pears(スケーティング・ペアーズ)』のサブ・レーベルだ。佐藤がディレクターを務め、組織らしい組織はつくらず、リリースごとにアーティスト本位のスタッフ構成で運営。現在となっては〈去りゆくのみ〉という感の強いCDメディアをメインに、エレクトロニクス/ノイズ/アンビエント──系の作品を、これまで8枚のCDアルバムとしてリリースしてきた。なぜいまCDなのか……とはよく問われるところだが、新作をアルバム形式で発表していくという目的上のサステナビリティにおいて、もっともリスクが少ない……とかなんとか並べていたら始まらないので、ここでは〈CDは
死 ね ず 〉とだけ記しておこう。
とにかくφononである。手前味噌ながら、初年のカタログ上にそろったCD8枚は、アーティストと音の質やヴァリエーションなど……押し並べて上出来だ。それぞれが自らのアクティヴィティをもって2018を彩ってくれている。ありがたいことだ。この彩りに「レーベルとしてなにかを添えなければならない」とディレクター佐藤薫は考えた。そこで選んだのは、出版した8枚のCDというフィジカル・メディアの総体を言語化しアニュアル・レポートとして提出する試みだ。
そして同時に閃きもあった(だろう)。神戸のバー”Arri”で催されたイベント『EP-4 Variationen』に、佐藤がかねてより「これは黒い音楽調書だ」と愛読していた『ランシエール 新<音楽の哲学>』の著者である市田良彦が姿を見せていたからだ。ミシシッピのデルタ・ブルーズからニューヨークの夜を経て、〈音楽の意味〉の意味が変調していく様態をドローンのように通底する「コール・アンド・レスポンス」をとおして思想するという非凡で珍無類の議論を白眉とする同書は、もっと〈音楽の側〉の読者を得るべきなのだが……。それはともかく、そこで佐藤は「そろそろあの本の続編が読みたい。だから書いてもらうことにした」──と、自分勝手な要望を市田さんに投げかけたのだ。
かくしてここに新<音楽の哲学>の続編を待望しつつ、期せずして“フォノン・アニュアル・マニフェスト 2018”と見損なうような、その〈序章〉を届けることがかなった。もとよりある視点から「音楽が最大かつ最終的な争点をなすはずである」という著者が、あらためて聴いた8枚のCDから、その消失点を展望する。
(小磯幸恵[φonon 事務局])
〈なにかが言われた〉
φonon :〈わたしたちの音〉をめぐるmanifesto
市田良彦
φonon :〈わたしたちの音〉をめぐるmanifesto
市田良彦
かくて今は…
フォノン・φononすなわち音量子。レーベルの名はそのように定められている。よってわたしたち聞き手は、個々の作品を聞くまえから、一つの二律背反を背負わされている──〈これは「作品」ではない〉。
量子は「粒子」(個体)とその周辺への「振る舞い」の両方である。わたしたちが聞くまでは、これが「作品=個体」になるかどうかは決められない。フォノンたることは、わたしたちをそんな準粒子の生成過程にいやおうなく巻き込んでいる。おまけに、あなたはこれを「作品」にしますか? と問われ、そうです、立派な「作品」です、感動しました、と答えた瞬間に、わたしたちは「これ」のほうを裏切ってしまう。「これ」からは、「作品」以前であること、あくまで「準」である質がぬぐえないのだから。「これ」を差し出したのは個々のミュージシャンであり、レーベル・プロデューサーたる佐藤薫である。「これ」を「作品」として理解し、消費したのでは、彼らの意志を裏切ることになってしまう。「これ」の「振る舞い」の決定には、彼らとわたしたち両方を含んでの〈わたしたち〉が、参画を求められている。未決の「振る舞い」を
ノイズ→音楽→〈わたしたち〉
近代の音楽は、聞こえるものの限界を突破しようとしてきた。まだ誰も聞いたことのない音楽を提供するために、音楽家は音楽のそとをなかに取り込もうとしてきた。ノイズは準楽音として、音楽のすぐとなりにありつつ、音楽家を〈あわい〉を操作する技術者にしてきた。雑音(ノイズ)と楽音、不快と快、音楽の無と有、醜と美が分かれ、ときに交じり合いながら交代する境界領域、〈あわい〉を。要は音楽として、また音楽のなかで、聞こえるものと聞こえないものの境界を。音楽家にとっては、音楽が宗教儀式の一部であることをやめた瞬間から、ノイズと楽音は「サウンド連続体」(シュトックハウゼン)を形成するようになった。彼は聞こえるものと聞こえないものの間に身を置きつつ、準世界である作品の原因、ゆえに世界そのものの準原因である存在のように振る舞いはじめた。「越境」は最近の流行などではないのだ。近代の最初から「主体」に課された義務である。音楽においても絵画においても文学においても、モダンな創造主は世界のはじまり以前の場所を、アートと非アートの〈あわい〉に見いだす。
宿命となった前衛イズム? そんなことはない。前衛はいつか発見する。わたしは大衆がやっていること以上のことをやらなかった、と。彼がなにかを発明したとすれば、それはすでに存在するものであったから、首尾よく結果を生む発明であることができた。〈あわい〉から出発する感覚的なものの操作技術は、とどのつまり、「作品」をはさんでわたしとあなたを一つの新しい〈わたしたち〉にする技術である。しかし、あらかじめ存在していないどのような〈わたしたち〉も、けっして見えるよう、聞こえるよう、理解可能なようにはならないだろう。共感の現出は共感能力の存在を前提にする。新しい〈わたしたち〉は、出来上がった瞬間に過去に投げ返される。ワーグナーは調性の乱れるオペラを通じて「ドイツ人」を作ろうとしたけれども、やればやるほど、彼は「ドイツ人」がすでにいた、「民族」は太古から存在した、と言わねばならなかった。「民族」の創生など不可能である、と認めたのも同然である。彼はその結論を否認したかったろうけれども。さらに、「管理された偶然」(ブーレーズ)を組織する程度のことなら、どんな「民衆」もすでにやっていると〈わたしたち〉は気づかずにいられない。前衛とは、自らについて誤解する近代的主体の謂いだ。時代の先を行っているつもりで、そのうち「大衆万歳!」と叫んで無責任に口を閉ざす。
技術⇆音楽⇆〈わたしたち〉
世界には様々な〈わたしたち〉がいる。あるいは世界というものは、様々な〈わたしたち〉からなりたっている。アメリカ人、アジア人、「日本国民」に加え、「ストリート系」に「音響派」、その他色々。作り手に聞き手、両者の共同体。今日では「ファンダム」も。なにがそれを成り立たせ、解体するかについても様々に語られてきた。想像、歴史、政治……。けれども、フォノンを構成する準作品群は、あらためてこの上なくシンプルな答えを提示してみせる。ノイズを音楽にする意志の技術だ。街角の音をマイクで拾い、メモリー媒体に信号として保存する技術には、そこを歩いて収音するというもう一つの技術がすでに重ね合わされている。編集技術の介入も予定されている。電子回路で一から音を生成する技術に、ライブ会場で即興的に音に反応する「パフォーマー」の技術が加えられる。音の伽藍を建築するのも、その塀に「落書き」したり内部の壁に穴を開けたりして空間を変質させるのも、同じように技術だ。そのうちきっと、AIに現場で「作曲」させて生バンドと共演させるコンサートも出現するだろう。将棋電王戦のように。とにかく、振動=信号が漂うテンポラリーな空間に〈わたしたち〉が浮上する。
AIを可能にするほど自立かつ自律しているかに思える物理的で物質的な技術も、こと音楽にかかわるかぎり、無媒介に身体に作用する技術であることを、ノイズミュージックは再確認させてくれる。文字や映像以上に、意志により「音」に加工されたノイズは主観的=主体的なのだ。意味なるものを通り越して、発信者と受信者を直結させてしまう。〈なにかが言われた〉と身体──耳には限定されない──を通して相互に了解させてくれる。電子回路のなかを飛び交う信号は、そとに発出されるや、わたしとあなたの間に自存する信号になる。発信者は最初の受信者でもあり(音を作っているとき)、信号はそのまま〈わたしたちの身体〉になる。音の無、沈黙もこの新しい身体の一部である。自然には存在しない加工音が耳から入って心臓の鼓動と一種の──あくまで一種だ──同調を果たしたとき、〈わたしたち〉が現れるのである。〈あなた〉と〈わたし〉は信号をはさみ、正確には振動=信号の両端として、いいも悪いもなく──感動とも嫌悪とも無縁に──共に現れてしまう。「器官なき身体」として? 少なくともこのテキストを綴っている〈わたし〉は、2018年9月23日、神戸で行われたライブ・イベント『EP-4 variationen』において現れた〈わたしたち〉にいまだ埋もれたままの〈わたし〉でしかない。
▲佐藤薫とEP-4 unitP w/HOSOI HisatoによるBaBaQueセッション Photo: TAKUMA SAI
〈わたし〉と〈あなた〉は〈わたしたち〉の敵
最初の言語は音声言語でしかありえなかった。〈わたしたちの音〉という意味の零度に、意味を乗せていくことから、言語ははじまった。というか、なんの意味もない信号の持続、なんの器官もない身体の存続に人は耐えることができず(しかし、なぜだろう?)、一方では信号を編成して「メッセージ」を乗せる努力が、他方ではそれを解読する努力がはじまる。受け取る側にとり、音群はETのメッセージか古代のヒエログリフのようなもの。彼/彼女の「反応」は、発信者に同じように受け取られるだろう。そんな発信と解読の応酬を通じて、たんなる、しかしすでに十分思わせぶりな音群は言語になっていく。応酬が続き意味が確定しない間は、〈わたしたち〉しかいない。発信者と受信者がたえず交代する間は、〈わたし〉と〈あなた〉は明確には区別されえない。「わたしはわたしである」と人が認知するためには、自分が発した信号の意味を、彼/彼女が知っている必要があるのだ。「わたしは~と言いたい」と自覚してはじめて、〈わたし〉は〈あなた〉から切断されて確定する。そのように言いたい〈わたし〉、独立した意志の主体として。ぼんやり〈なにか〉が言いたいだけではだめなのだ。この順序を間違えないようにしよう。はじめに〈わたしたち〉が〈あわい〉に現れる。それが意味の確定を通じて、〈わたし〉と〈あなた〉に分裂する。
しかし、意味はけっして自動的には生成されない。信号のやりとりそのものに、意味を決定する力はない。だから「文化」や「歴史」、さらに「権力」さえ語られるのだが、逆にどのような意味、どこから持ち込まれる意味も、信号のやりとりと〈わたしたち〉の形成を通じてしか実現されない。はじめは〈言われたなにか〉と感知される音のそと、そとの音は、音空間のなかを行きかう「空白の仕切り」──有意な差異──にならなければ「意味」に変換されないのである。つまり、ここにも〈あわい〉がある。いや、ノイズとは意味のない音としか定義しようのないものであるから、楽音のそとと未決の意味は実体的に同じである。二つの〈あわい〉は重なり合っており、ノイズを楽音にする音楽の歴史はそのまま言語的意味全体の歴史を、つまり世界なるものの歴史を擬態している。
重なり合う交点に〈わたしたち〉がいる。だとすれば、〈あわい〉はもう一つある、あるいは事後的にもう一つ出現する、と言うべきだ。音と意味が結合して〈わたし〉と〈あなた〉を弁別するようになると、〈わたしたち〉はその両方にとって「敵」にならざるをえない。〈わたしたち〉は〈わたし〉と〈あなた〉に先立つ故郷にして両者の無であったのだから、今となってはいずれからも個体性や主体性を奪うもの、という規定を逆に受け取ってしまう。意味と無意味、人間とモノや自然、「霊魂」と「肉体」のちょうど中間、両者の間仕切りだ。人格を解消させる過剰に物質的な死の地帯であり、ノイズに代わって無意味を背負う匿名の人格であり、とにかくそれとの距離によって〈わたし〉と〈あなた〉、世界と意味、世界の意味が安定していられる場所である。〈わたし〉と〈あなた〉が自らの出自に悩まない──神が〈わたしたち〉を作ったのははたしてよきことであったか?──ためには、信号ととともに成立した
フォノン:〈わたしたち〉の帰還
いつのころからか、それを忘れるために音楽は使われてこなかったか。名前(=アイデンティティ)をもたず、名前を否定するかのような〈わたしたち〉に、〈わたし〉や〈あなた〉と同じような名前を与えるために、「ジャンル」や「技法」が代替使用されてこなかったか? 音階やリズムに「~人」たることを結び付ける人種主義の愚が終わったあとも、音楽に「トライブ」を形成させる欲望はむしろ自覚的に強められているだろう。どんなに地理的・言語的・文化的・歴史的に隔てられている人間であっても、音楽によってなら「分かり合える」。同族集団に帰属することができる。〈わたし〉や〈あなた〉はそう知ってしまった。音楽を差異化し増殖させることで、〈わたしたち〉を〈わたし〉
そのただなかにあって、これはノイズミュージックであると名のり、粒子ならぬ量子であると宣言する、佐藤薫たちの試みはどうしたってメタ音楽的な意志を響かせずにはいない。音楽から音楽を作る音楽がノイズだ、世界がノイズだ……。今日主流となった音楽の聴き方──〈わたしたち〉を享受/享楽する方法である──が、イヤホンでそとの音を遮断しつつ街を歩くこと、オンオフの二動作を同時に行うことであるとすれば、〈わたしたち〉はなるほどすでに俄かノイズミュージシャンではないか。そんなことさえ、これらの準作品を聞く〈わたしたち〉は思い知らされる。しかし、あくまでもノイズ、一つのアンビエンス(環境)でしかないと断って提示されるこれらは、〈なにか〉しか語らない。ここにあるのは音楽のミックスではなく、あくまでも音楽以前である。なにも言わない〈なにか〉にとどまろうとしている。どんな意志も抹消する意志。非意志的な意志。彼らはまるで現代の修道僧のようだ。フォノンは〈わたし〉を〈わたしたち〉に連れ戻す。主体を空っぽの箱にする。これら/彼ら/わたしたちは、今や世界の「敵」である。
そしてある日に…
以下に読まれるのは、この2018年にスタートしたフォノン・プロジェクトを構成する最初の8枚のアルバムを、二度目にランダムな順序で休止なく聴いた〈わたし〉の脳に映じた、〈わたしたち〉をめぐる一枚の絵である。フォノンを構成する9枚目のアルバムを仮構しつつ、つまりもう一つのなにも言わない〈なにか〉として、〈わたし〉はそれを記録に残したい。
▲EP-4 [fn.ψ]: OBLIQUES (SPF-001)
〈わたし〉は「踊って」いたのだろうか?:返歌としてのOBLIQUES
なぜ鳥は歌うのか?──ほかの鳥の歌を聞いたからである、とメシアンは自問自答した。その答えが正しかったとすれば、EP-4 [fn.ψ]の名により差し出された『OBLIQUES』──「いくつもの斜線」と訳したい──は、なにより80年代EP-4への返歌であり、かつ、かつての歌の上に引かれた斜めの線である。〈わたしたち〉はそう聞いてしまう。かつてのようには踊らせない、もはや。電子音の重たい
▲HOSOI Hisato: BaBaQue (SPF-005)
一人の人類が歌い踊る:BaBaQue
よいではないか、かつてのようであっても、とHOSOI Hisatoの『BaBaQue』は語る。あそこから切れ目なく続く今もまたあるではないか、と。「ファンク」が宇宙のOne Nationを目指して上っていかず、足元を掘り進み、現代の「クラブ」を土俗に還す。あのころと今、こことよそ、はつねに直結している。それを知るにはどこへも行く必要がなく、様々な音源モジュールをつなぐ技術さえあればいい。この身体の「踊り」が媒体に──編集作業の基準に──なってくれる。ただし、BaBaQueに踊ってしまえば、もう「クラブ」では踊れない。「トランス」のなんと退屈なことよ、皮相なことよ。BaBaQueに踊ってそう思い知らされつつ、〈わたし〉は頭のなかに箱を作り、そこで無名の部族になっている。たった一人でも、〈わたし〉は人類だ。いや、たった一人の人間は、まさに一人しかいないのだからすでに「類」である。そう主張したのはルソーであったか。彼は実際にオペレッタ「村の占い師」を作って、「村人」に実体を与えようとしたけれども、一人を即自的に全員にする歌―踊りもまた存在するとBaBaQueは告げる。ここでは予期は、心地よくかつ不快に満たされ、裏切られる。なにしろ、「パリ、テキサス」がライ・クーダーを通り越してブラインド・ウィリー・ジョンソンに帰り、2018年のここに降り立つのだ。
▲Jun Morita: LʼARTE DEI RUMORI DI MORTE (SPF-004)
一人で集団即興演奏する:LʼARTE DEI RUMORI DI MORTE
ランダムに、この2枚からはじめたつもりだった。しかし〈わたし〉は、そうではなかったと、Jun Moritaによる『L’ARTE DEI RUMORI DI MORTE』──「The Art of Death Noise」──に二度目の手を伸ばして覚る。最初の2枚を連続して聞いたのは、どこが似ていて似ていないかを確かめたくなったからであったと、両者とはまったく異質の3枚目が気づかせてくれる。佐藤薫がBaBaQueの編集に参加していると知ったのはこれを書きはじめる直前、つまりL’ARTE DEI RUMORI DI MORTEを聞いた後だった。「デス・ノイズ」に擬せられているとはいえ、そこにある音は、踊りのある/なしとはまったく違う示差的境位に〈わたしたち〉を連れ戻す。これは、DJの手法で再現されたフリージャズであるのかもしれない。ドン・チェリーの「エターナル・リズム」、オーネット・コールマンの「フリージャズ」、ある時期のアート・アンサンブル・オブ・シカゴ、等々。数名のアンサンブルが、いわゆる「テーマ」(旋律)とは別のラフな規則だけを前もって共有し、よーいドンで集団即興演奏をはじめる。ポリリズムさえなさないずれた複数のリズム、あちこちに飛ぶメロディーの切片群が、次第に感応しあって〈共〉を響かせる。それを一人で、それぞれのモジュールを複数のターンテーブルを同時に回すようにして重ね合わせ、再現する。OBLIQUESとBaBaQueがともにもったような、出発点にして持続的にベースとなる
▲Axel Dörner: unversicht (SPF-007)
〈わたし〉の息の向こうに〈わたしたち〉が…:unversichtの解剖学
その「国」からこのアルバムを経由して、これまたただ一人──Axel Dörner──の手になる『unversicht』に伸びる線は、ジャズのなかにも走っていた近代音楽の正統精神を再浮上させてくれる。音と非音の〈あわい〉に生じる反響に、〈わたし〉と〈あなた〉の関係を重ね合わせ、新しい共同体のモデルとすること。しかし、バンドが野に生まれ育つ「俺たち」の住まいで、室内楽アンサンブルがブルジョワ家族の理念型で、オーケストラが端的に国家像であるその一方、物質的で身体的な音と未知の集団精神の間をつなぐのは、「アーチスト」個人の創造性であったり実験精神であったりする。「アート」と〈わたしたち〉の特殊近代的な関係はきわめて独我論的なのである。集団即興演奏は、実は一人でも行いうる音楽であるのでなければならず(L’ARTE DEI…)、電子の音は生物としての
▲Radio ensembles Aiida: From ASIA [Radio Of The Day #2] (SPF-002)
〈わたし〉を満たす遠くの音:From ASIA
だから近代音楽の王道であるノイズミュージックは、「見える」と「見えない」のこの隙間、身体と魂の間の空虚であるこの〈わたし〉を、ただ満たそうとしているのである。空っぽになったこの場所に、そとの世界を呼び込んで。そのことを、一人であるけれども複数形で名乗るRadio ensembles Aiidaによる『From ASIA』はみごとに証言していよう。空虚な密室である〈わたし〉に、遠くから、ラヂオの音が飛び込んでくる。街頭の喧騒、風の音、アナウンサーの声、既存の音楽は、電波により無差別にノイズに変換されて〈わたし〉を満たし、〈わたし〉なるものは、複数のノイズを干渉させて今ここの音を合成する半ば意志的な、半ば無防備に成り行き任せの行為に縮減される。かくて「〈わたし〉すなわち世界」という構図が完成される。そして、ここが肝心だと思われるのだが、そうなってはじめて、近代音楽はその独我論的宿命から解放されるのだろう。なるほど、世界に一致する〈わたし〉とは自我の専横の極致のように見える──世界は〈わたし〉次第だ!──ものの、この〈わたし〉たるや、中身を徹底的に吐き出してしまった自我の残骸、あるいは残骸としての自我にすぎず、世界との一致はいわば「城の明渡し」による「おまけ」にほかならない。From ASIAがサウンドスケープなら、サウンドスケープは「エコロジー思想」──環境(アンビエント)と共生せよ──とはなんの関係もなく、むしろ一種の「禁欲主義」である──自意識を消去して〈わたし〉を造物主に引き渡せ。
▲Singū-IEGUTI: Diffraction (SPF-006)
このアンビエントはほんものか?:Diffraction
しかし、〈わたし〉のなかに引き入れられた世界は、はたして〈わたし〉のそとに実在しているのだろうか。なるほど、電子回路によって〈わたし〉の神経がそとに拡張される感覚を、トリオ ・プロジェクトSingū-IEGUTIによる『Diffraction』──「回折」──は味わわせてくれる。耳は360度の周囲から音を集め、脳のなかに空間を再現しているけれども、Diffractionはまるでそれが反転し、脳から出ていった音が〈わたし〉を包むアンビエントを作るかのような錯覚を、音の「回折」によって生む。まるで母親の胎内に戻ったかのような感覚を、「屈折して回り込む」という波動の特性によって教えてくれる。しかし、ふと我に帰れば、みな知っているではないか。誰も母親の胎内にいたときのことなど憶えていない。この「そと=アンビエント」は偽物だ。〈わたし〉がそとに出て行ったのでもないし、そとが〈わたし〉に入ってきたのでもない。拡張感は音の効果でしかないのだ。またしかし、音源をオフにしてもほかの音が入ってくるだけで構造的にはなにも変わっていない、とも〈わたし〉は気づかずにいられない。〈わたし〉は聴覚を通してこの世界とかかわっているのであり、だとすればつまり、〈わたし〉はそもそも世界を「そとにある」と錯覚している?
▲Various Artists: Allopoietic factor (SPF-003)
▲Various Artists: Mutually Exclusive Music (SPF-008)
世界を集める/作るコンピレーション:Allopoietic factor/Mutually Exclusive Music
隣にいる〈あなた〉も同じように疑問に思っているかもしれない、と〈わたし〉は思う。これはどこから聞こえる誰の音? ほんもの?──〈あなた〉もそう自問しているのではないか、と。ならばとりあえず、それぞれに世界がどう聞こえているのか交換してみよう。互いに
それに対し、この世界がほんとうに実在すると確信するためには、一から作ってみるほかない、と、もう一枚のコンピレーション『Mutually Exclusive Music』に集った〈わたし〉
いずれにしても、コンピレーションとは「多」である。二枚のアルバムには「多数の世界」がある。しかし、「多」になった瞬間、「1」の実在性は縮減される。これも可能あれも可能、では、個々の「1」はtwitterの「つぶやき」とどう違う?「0」に「戻る」ないし「向かう」圧力を「多」から受けてしまう。「あなたの音はいつも例外」(Jun Morita、 ≪ Irregular are the voices I hear ≫)であるなら、つまりこの「いつも」こそほんとうであるなら、「例外」など存在しないではないか。「あなたの音」が「あなたの音」であるのかもはや怪しいではないか。彼らはそれを知っているのだろう。だから集ったのだろう。集うことで減衰・縮減されると知っていながら「1」の現出に挑むべし。二枚のアルバムはそう言っているかのようである。そうでもしなければ、「つぶやき」の群れが〈わたしたち〉を占領してしまうではないか、〈わたし〉は「ビッグデータ」に呑まれてしまうではないか、と。二枚のノイズ群は、ノイズになった──なにも言わなくなった──世界への静かで狂おしい抵抗だ。
フォノンによって再構築された世界も、〈わたし〉のそとの世界も、同じ運命に従うほかない。ノイズは、いつか聞こえなくなるのである。反復に抗えば記憶されず、反復されれば、いかに音量を上げても音の強度は失われていく。そういうふうに聴神経はできている。それを知らしめるためにだけであっても、フォノン・プロジェクトは当分終わりを迎えられそうにない。ああ、いつか音楽を世界の隠喩としなくともすむ日は来るのだろうか。
市田良彦 プロフィール
神戸大学国際文化学研究科教授
著書に、『闘争の思考』(平凡社 1993年)・『ランシエール 新<音楽の哲学>』(白水社 2007年)・『革命論 マルチチュードの政治哲学序説』(平凡社新書 2012年)・『ルイ・アルチュセール 行方不明者の哲学』(岩波新書 2018年)──など。ほかに共著書/訳書など多数。
■リリース情報
EP-4 [fn.ψ]『OBLIQUES』
EP-4 [fn.ψ] photo: Yoshikazu Inoue & Eizaburo Sogo
φonon
2,000円(税抜)
SPF-001
2018年2月18日リリース
解説:山本精一
EP-4の佐藤薫とPARAやEP-4のサポートなどマルチに活動する家口成樹の2人によって2015年に組まれたユニットEP-4 [fn.ψ]。ラップトップ・ガジェット、シンセサイザー、エフェクターなどが織りなす即興的音の立体空間は、ノイズでありアンビエントでもあるという対語的多面的要素を見事に融合した音のアマルガムを構成する。「OBLIQUES」は2017年6月大阪で行われたライヴの演奏を収録した作品だ。ときにストリームのように、ときにはフィルミーに立体的な音空間を織りなすライヴ丸ごと60分。ノンストップのノイズ・セット!
Radio ensembles Aiida『From ASIA (Radio Of The Day #2)』
Radio ensembles Aiida
φonon
2,000円(税抜)
SPF-002
2018年2月18日リリース
解説:富田克也
Radio ensembles Aiidaは、異色の女性ソロBCLパフォーマー A.Mizuki によるソロ・サウンド・ユニット。複数のBCLラジオが偶然織り成す一期一会の受信音と、リレースイッチの電流制御などによって生まれるビート/グルーヴをコンダクトし、類を見ないサウンドスケープ的な音世界を紡ぐ。前作では自室の音風景を切りとり繊細かつ大胆な不思議空間を表現していたが、本作ではタイトルどおり、BCLチューナーを抱えて訪れたアジアの街角でのフィールド・レコーディングで構成された不思議空間を創出している。
Various Artists『Allopoietic factor』
φonon
2,000円(税抜)
SPF-003
2018年6月15日リリース
解説:大谷能生
シンセ奏者/サウンド・クリエイター/プロデューサーの家口成樹が選曲/編纂したコンピレーション・アルバム。PARAやEP-4、自身のソロ・プロジェクトkruispuntなどで活動する寡黙なる男が、その鋭い触覚で国内エレクトロ系アーティストをチョイス。若手からベテランまで含めたその10組のアーティストは──ZVIZMO/TURTLE YAMA/bonnounomukuro/Singū-IEGUTI/Yuki Hasegawa/4TLTD/Natiho Toyota/black root(s) crew/Radio ensembles Aiida/EP-4 [fn.ψ]──(収録順)
Jun Morita『L'ARTE DEI RUMORI DI MORTE』
Jun Morita
φonon
2,000円(税抜)
SPF-004
2018年6月15日リリース
解説:佐藤薫
都会の夜を未来主義的超散文原動機で切り裂くモデュラリスト、森田潤の初ソロCD。DJ/映像作家/クリエイターとして活躍する森田による混沌と恍惚の美学をディスクに凝縮。あらゆる音のエレメンツを、ノイズのカケラでさえも、マッシヴに乱反射させて危ういサウンド・コラージュへと進化させる類い希な音響センス。2018年5月に上演の芥正彦企画/演出によるノイズ・オペラ「カスパー」の音楽を佐藤薫と共に担当するなど、フィールドや手法を越境する森田の新境地がここに!
HOSOI Hisato『BaBaQue』
HOSOI Hisato
φonon
2,000円(税抜)
SPF-005
2018年9月21日リリース
解説:今野裕一
HOSOI Hisatoは、’83年に”謎の少年楽団”としてカセットブックを発表し現在も活動を続ける”チルドレンクーデター”の首謀者であり、ボアダムスのオリジナルメンバーとしても知られるなど、10代から関西アンダーグラウンド・シーンを支える要人のひとり。そのホソイの実に27年ぶり2作目となるソロ・アルバム『BaBaQue (ババケ)』は、作曲、ベース、打ち込みからシンセサイザー、サンプリング、素材コラージュ、ミックスなどの制作工程をホソイ自ら手がけた渾身の1枚。切れ味鋭いノイズとビートが、聴く者の脳裏に潜む闇の記憶を不気味に想起させる。
Singū-IEGUTI『Diffraction』
Singū-IEGUTI photo: pasar aki
φonon
2,000円(税抜)
SPF-006
2018年9月21日リリース
シンセ奏者としてマルチに活動する家口成樹が、広島県在住のKIYOとKETA RAの兄弟ユニットSingūと融合反応したトリオ・プロジェクトがSingū-IEGUTI(シングーイエグチ)。初のアルバム『Diffraction』は、穏やかで知的な音楽感性をもつ家口らしいアプローチと、プログラミングやエレクトロニクスのほかギターやドラムなど生楽器も取り込むSingūの柔軟性が織りなす即興演奏をもとに、美しく精緻で濃厚なアンビエント~エレクトロニカ色の漂う作品に仕上げている。太古によみがえる未来へと身をゆだねるべき悠久の時間がここに流れる……。
Axel Dörner『unversicht』
Axel Dörner
φonon
2,000円(税抜)
SPF-007
2018年12月21日リリース
解説:佐々木敦
日本でも大友良英など多くのアーティストとのコラボレーションで知られるドイツ出身の即興トランペット奏者アクセル・ドナー渾身のソロ・アルバム。ジャズやクラシック、フリーインプロヴィゼーション等、ノンジャンルなセッション活動を旨とする彼がその一方で、異形の演奏技術と電子的に拡張/メタモルフォーゼさせたトランペット音による実験を独り重ねてきた成果がこの「unversicht/ウンフェルジヒト」だ。加工され拡張し変形され編集することで生まれる多様な音像が、音韻的変化を想起させ、類い稀なるソロ・アンサンブルを構成している。
Various Artists『Mutually Exclusive Music: Modular Synthesis Roundup』
φonon
2,000円(税抜)
SPF-008
2018年12月21日リリース
解説:小林径
森田潤、中原昌也、一楽儀光、そして齋藤久師──4人のモジュラリストによる世界に類を見ないモジュラー・シンセのコンピレーション・アルバム。ここ数年で大きな話題となり、世界中の大小メーカーがこぞって参入するモジュラー・シンセ市場には、千種を超えるともいわれる様々なモジュラーが流通。しかしハード先行の話題がともすれば音楽そのものに《?》を投げかける今、このアルバムがその疑問符へのメルクマールとなる。タイトルは、プログラミング/パッチングの選択的緻密さがある意味で反音楽的に作用し、音楽作品として相互排他的に決定するイベント/事象をシニカルに表している。
■ライヴ情報
『”Mutually Exclusive Music: Modular Synthesis Roundup” CD Release Party』
2019年1月14日(月祝)秋葉原 CLUB GOODMAN
Open/Close 17:30~22:00
料金:前売3,500円 当日3,800円
ライヴ:森田潤、Hair Stylistics (中原昌也)、DoraVideo、齋藤久師
ゲストライヴ:ZVIZMO (伊東篤宏+テンテンコ)
DJ:小林径
照明:F∞x Laser a.k.a 1∞take
秋葉原 CLUB GOODMAN
東京都千代田区神田佐久間河岸55 ASビルB1F
http://www.clubgoodman.com/blog/?p=15848
▼Annual Manifesto 2018
φonon公式サイト
http://www.slogan.co.jp/skatingpears/
φonon試聴サイト
https://audiomack.com/artist/onon-1
φonon YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCLEoeDAR9eGHLUI4yVZE5ug